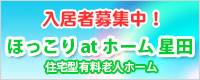嚥下機能低下が起こってくる状況
「むせやすい」「飲み込みに時間がかかる」
こうした変化は嚥下(えんげ:飲み込む力)の低下のサインです。近年では「口腔機能低下症」として保険診療で診断できるようになり、多くの歯科診療所で対応が進んでいます。
嚥下低下が起こる背景
口や顔のまわりは、頭頚部の中でも特に多くの筋肉が交差しながら働く部位です。舌や咀嚼に関わる筋肉は意識して動かせる「随意筋」が多く、普段からしっかり動かしていないと、筋肉が硬くなったり使われなくなったりして、自然と嚥下機能が弱っていきます。
嚥下機能が低下すると「むせ」が起こりやすくなります。これは咳反射という防御反応で、食べ物や飲み物が気管に入らないよう体が自動的に働くものです。しかし舌の動きや咀嚼の不十分さなど、口腔内の機能低下が背景にあることが少なくありません。
飲み込む仕組み
食べ物が口から胃へ届くまでには、
- 歯と舌でかみ砕き、食塊(しょっかい)をつくる
- 舌が後方に送り込み、咽頭へ運ぶ
- 喉頭蓋(こうとうがい)が気管を閉じ、同時に食道が開いて食塊が流れる
という流れがあります。
実はこの「飲み込む瞬間」はわずか0.5秒程度。とても短いですが、体は自動的に正確なタイミングで働いています。
イメージとしては、駅の自動改札に切符を通すときの一瞬の動きに近いでしょう。通過は一瞬でも、その裏で複雑な仕組みが正確に働いているのです。
改善・予防のためにできること
嚥下そのものを直接強めることは難しい面がありますが、
- 開口トレーニング(口を大きく開ける練習)
- 舌の可動域を広げる運動
- 発声・発語訓練
- 顔まわりや首の筋肉のマッサージ
などで血流を良くし、筋肉の働きを活性化することは可能です。日常的に口や舌をしっかり動かすことが、嚥下機能を守る大切なポイントです。
次回は、嚥下機能とも深い関わりのある「顎関節」の問題について解説していきます。